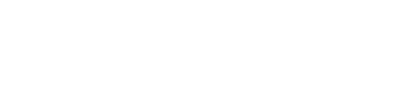東京本染ゆかた「注染/染色編」

型付けを済ませた反物は、注染台に移されます。染色の前に、多色のゆかたの場合、色が混じらないように別の色が染められる場所に糊の堤防が作られます。バースデイケーキに名前が書き込まれるように、堤防が作られている様子がお分かりになりますでしょうか。

いよいよ染色の作業に進みます。左右に持った「じょうろ」のようなものは「やかん」と呼ばれ、それぞれに別の色の染料が入っています。左右に持ったやかんの染料を先ほど作った堤防で仕切られたスペースに注ぎ込みます。注がれた染料は、折り畳んで積み上がった反物一枚一枚に浸透しながら、下から空気で吸いとられる仕組みになっています。

左右の手に持ったや「かんに」は、濃淡の染料が入っていて、手先の感覚ひとつで微妙な注染のボカシが染められていきます。
染める職人が注文主の意図をどう解釈するかでも染め上がりにはかなりの違いがでます。同じ型を使っても、前年に染めたゆかたと今年染めたものでは、かなり違った上がりになるのです。もちろん、職人によっても違ったものになることはお分かりいただけると思います。ここが、注染ゆかたの一番の魅力といえるかも知れません。
染色が済むと裏返され、裏側からも同じ作業を繰り返します。糊の堤防を築き、「やかん」での注染。このとき、表側と同じ色の染料を注がなくてはなりません。今は間違えることはなくなったとおっしゃるベテランの職人さんも、若い頃には間違えたこともあったそうです。間違えれば、重ねた反物の全てが不上がり品になってしまうという、結末が待っています。

注染が終わると、全体に水が注がれ、余分な染料が洗い流されます。
防染糊が落とされると、美しい模様が。注染独特のボカシは、このような作業から生まれるのです。より近代的な染色技法が生まれ、より大量生産が可能になってはいますが、このボカシの美しさを完全に表現することはできません。今でも東京の空の下で、黙々と仕事に取り組む職人と、工場があることを多くの皆さんに知っていただきたいと思っています。

染色が終わった反物は、「水元(みずもと)」と呼ばれる洗い場で糊と余分な染料を落とし、天日で乾燥させます。そして、ドラム式の大きなアイロンで仕上げ加工を施され完成となります。
この注染(ちゅうせん)の技法が誕生したのは大正時代。それまで長板(ながいた)と呼ばれる1反1反しか染められなかった時代には画期的な染色技術でした。そこからすでに80年以上がたち、より印刷に近い方法で染色もできる時代になっています。
大量生産大量消費、そして生活者の格安志向の高まりという時代背景の中で、注染の工場も廃業が相次いでいます。東京、浜松、名古屋、大阪と日本各地で今も続けられている注染の仕事。これからも味わいあるゆかたや手拭いを私たちが手にできるよう、工場の灯が守られていくことを願ってやみません。
「東京本染めゆかた 型付け編」はこちらをご覧ください。